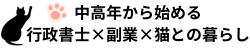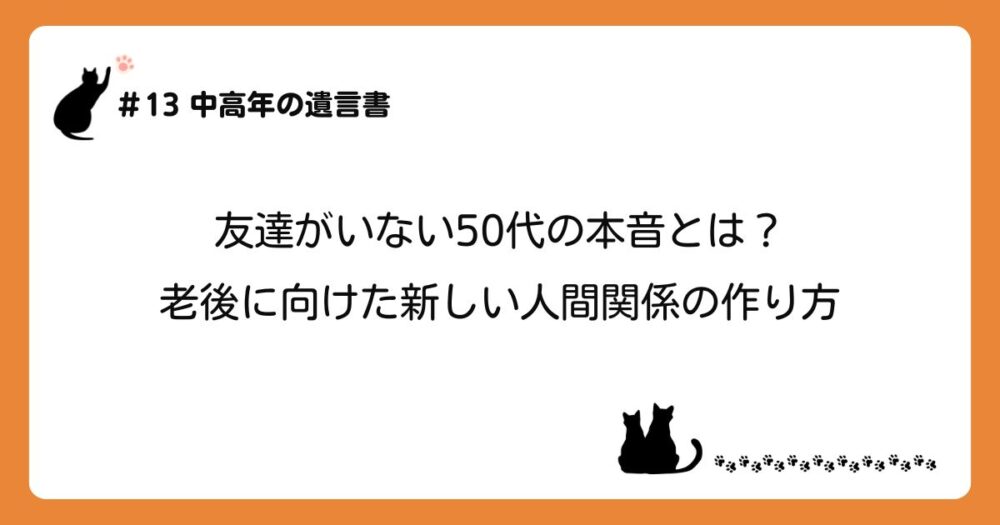30代、40代と年齢を重ねるに連れ、徐々に友人と会う機会がなくなり、50代になってから「友達がいない…」と不意に寂しさに襲われることがある。
仕事終わりや休日は自宅でゴロゴロしているだけ。急激に気力や体力も衰えを感じ始め、そもそも人付き合いも億劫になりがち。そんな日々を過ごしていたら、老後に向けてますます人間関係が希薄になっていくのは明白だ。
独身のまま50代を迎えた私は、「一人で過ごすのは嫌いではないけれど、友達がいないのは少々寂しい…」なんて、なんとも矛盾した考えを持っている。しかし、私と同じような感情を抱く中高年世代は少なくないのではないか。
「友達がいないからといって、特に支障はない。それでもチャンスがあるなら、新しく気の合う友人を作りたい」——そんな友達がいない中高年男性に向けて、50代からでも遅くない新たな人間関係の作り方について、自分自身の体験談を中心に紹介していく。
友達がいない50代が抱く孤独感の正体とは?
50代になると襲われる得体の知れない孤独感について、まさに友達がいない私自身の経験に基づいて、その正体を暴いてみる。
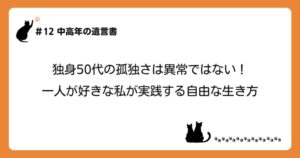
人付き合いの減少による孤立感
人付き合いが減り始めるのは、50代からという訳ではない。30代になった頃から仕事の忙しさや結婚などをきっかけに、仲の良かった学生時代の友人とも徐々に疎遠になっていく。
40代はさらにその傾向が強まり、50代になると昔の友達と交流があるのは、年に一度の年賀状のやりとりくらい。昨今の年賀状じまいの流れもあって、生存確認すらできない知り合いも少なくない。
そしていつのまにか、「あれ?もしかして、俺には友達がいない⁉」なんてことに……。新たな人間関係を作るのが難しい50代になって、友達がいない事実を突きつけられると孤立感が否めなくなる。
気力や体力の衰えからくる無力感
40代までは「まだまだイケるかも!」と年齢による衰えを感じない人も多い。しかし、50代になると、明らかに気力や体力が続かないことを実感する。
そして、気力や体力の衰えを感じ始めると自分に自信を持てなくなり、「俺の人生は終わった…」と大きな無力感に襲われてしまう。
アントニオ猪木の「元気があれば何でもできる!」は有名な言葉だが、気力や体力が衰え始めると「元気がないから何にもできない…」なんて状態になりかねない。
仕事もプライベートも成長を感じられない停滞感
50代で襲われる気力や体力の衰えは、仕事やプライベートにも大きな影響を及ぼす。
仕事では出世や昇給のチャンスがなくなり、プライベートでも新しい挑戦をする意欲が失われる。まるで何をしても成長を感じられない停滞期に突入したような感覚に陥っていく。
若い頃であれば、停滞感に見舞われても時間が解決してくれるが、50代を過ぎると残された時間は少ない。時間の経過は解決どころか、人生の終焉が近づいている寂しさだけを感じるようになる。
職場や家庭で必要とされなくなる喪失感
昔からの友達との交流が途絶えるだけでなく、職場では窓際に追いやられ、家庭では妻や子供からも必要とされなくなる。そんな喪失感に襲われている50代男性は多いのではないか。
私は独身のため、家庭のことは良く分からない。しかし、これまで頼りにされていた「夫」や「父」の立場が徐々に失われていく寂しさは想像に難くない。
仕事関係の付き合いも多く、家庭を大事にしてきた人ほど、自分の周囲から人が離れる現実は、50代の孤独感を一層深めていく。
老後を迎える漠然とした不安感
50代を迎えると、老後を迎える不安感が一気に増す。40代までは冗談半分に老後の生活を語ることはあっても現実感はなかった。
しかし、50代は違う。定年も間近に迫り、老後資金や健康問題など、将来に直面する課題が現実味を帯びてくる。
常にどこか身体の不調を感じる日々。そして友達がいないという現実。「この先どうなるのか…」という漠然とした不安を抱いてしまうのも無理はない。
老後の楽しみが増える50代からの人間関係の作り方7選
友達がいない50代でも、新しい人間関係を作ることはできる。ここでは私自身の体験談を中心に実践的な方法を7つ紹介していく。
セカンドキャリアに挑戦する
セカンドキャリアに挑戦することは、新しい人間関係を作る大きなきっかけにもなる。中高年世代にとって、仕事を通じた出会いが最もハードルが低いと言えるだろう。
とはいえ、「50代の転職なんてリスクがデカ過ぎる…」と思うかもしれない。だが、新しい仕事をするために必ずしも転職は必要ではない。
現在の仕事を続けながら、まずは副業として興味・関心のあることを始めてみるのも良い。次に紹介するSNSの利用は、セカンドキャリアに向けた人脈作りの助けになるはずだ。

SNSで情報発信を行う
中高年世代でもYouTube動画を視聴したり、InstagramやXで情報収集したりする人は珍しくなくなった。しかし、SNSで情報発信をする人は決して多くない。
だからこそ、50代で情報発信を始めることは希少価値がある。まさに「50代で友達がいない不安」や「50代からの終活準備」などの日常を発信すれば、競争相手も少なく共感もされやすいため、フォロワーも獲得しやすい状況だ。
前述したセカンドキャリアに向けた仕事仲間を見つけるきっかけにもなる。私はセカンドキャリアとして考えていた行政書士のほか、興味のあった副業や保護猫の情報発信をして、半年程度で約2,000人のフォロワーを獲得することができた。
もし、SNSの情報発信が当たり前の20代や30代だったら、500人のフォロワー獲得すら難しかったかもしれない。だからこそ、50代の今だからこそチャンスがある。
【保護猫の紹介】
— ねこさち|保護猫の本音 (@nekosachi_4949) March 28, 2023
◆しらす♂(右上)
性格:ビビりで甘えん坊
特徴:ピンクの鼻とハートのかぎしっぽ
◆にぼし♀(右下)
性格:ツンデレ女王様
特徴:まん丸おめめとスリムなしっぽ
【その他登場生物】
◆地域猫コマリ♂♀?
◆保護亀カメオ♂♀?
◆おじさん♂等
★リプ欄で猫が本音をつぶやきます pic.twitter.com/qH8jXyB6fu
資格やビジネスの講座を受講する
SNSに魅力を感じながらも、セキュリティや炎上のリスクが気になって、どうしても足を踏み入れたくない人もいる。
そんな人には、資格やビジネスの講座を受講するのがおすすめだ。ネットとは異なり、リアルな人間関係を作りやすい環境がある。時間に余裕がなければ通信講座で学ぶのも良い。
今の中高年世代が学生時代に利用した通信講座とは違い、授業内容の質問や回答もリアルタイムのやりとりが可能な講座も多い。
定期的に送られてくるテキストや問題に一人で取り組むのではなく、同じ目的を共有する仲間との繋がりを感じられる点も魅力だ。

趣味や運動のスクールに通う
「仕事ではなく、プライベートで人と関わりたい」──そんな人には、趣味や運動のスクールに通うのも有効な選択肢の1つだ。
釣りや料理、フィットネスジムやヨガなど、老後に向けた趣味作りや健康の維持改善としても最適なため、50代から始めるメリットも大きい。
プライベートな空間でリラックスして取り組めるからこそ、気の合う仲間も作りやすいと言えるだろう。「50代からの友達作り」という観点では、一番の方法かもしれない。
町内会の活動に参加する
年齢を重ねると、ボランティア活動でもして「誰かの役に立ちたい」と思うようになる。しかし、大抵の人は興味を持つだけで実際に行動するまでには至らない。
その点、地域のボランティアとも言える町内会の活動は、一定の周期で回ってくる班長や役員の当番など、半ば強制的に参加を強いられる。 それが、消極的になりがちな50代にとっては、人間関係作りの後押しになる。
定期的な会合のほか、行事の手伝いや防災訓練などを通じて、自然に会話をするタイミングも生まれる。 ご近所付き合いが薄れた今、町内会活動は地域とのつながりを持てる数少ない貴重な機会だ。
友達とまではいかなくても、困ったときや災害時に助け合える関係があるのは心強い。地域社会に貢献できることは、老後の生きがいにもなるだろう。
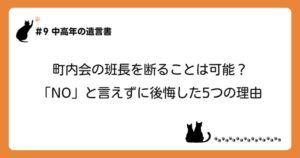
昔の友人ともう一度つながる
現実的には、50代になってから学生の頃と同じような友達を作るのは難しい。だからこそ、昔の友人に思い切って連絡して関係性を取り戻すのが、一番簡単な方法かもしれない。
50代は仕事やプライベートでも40代の頃と比較すると、少しずつ落ち着きが生まれる年代。忙しくて疎遠になっていた友人に久しぶりに会うには絶好のタイミングだろう。
学生時代の思い出話はもちろん、仕事の失敗や老後の心配も酒のツマミになる。それは、昔からの友人だからこそ。
毎年のように年賀状の一言で「今年こそ皆で飲もう!」なんて書くのではなく、〇月に連絡するから、久しぶりに懐かしの居酒屋〇〇で飲もう!」と具体的な誘いをしてみてはどうだろうか?
マッチングアプリに登録する
独身や離婚経験のある人で、友達から発展して結婚や新しいパートナー作りを望んでいる人には、マッチングアプリも試す価値がある。
中高年世代はマッチングアプリと聞くと、「若い人が使うもの」「詐欺やパパ活が怖い」など否定的なイメージを思い浮かべるかもしれない。
しかし、今や東京都が少子化政策としてマッチングアプリを利用している時代。使い方さえ間違えなければ、効果的な出会いのチャンスが生まれる。
私が現在仕事の1つとして携わっているWebライターの案件でも、マッチングアプリに関する記事は作成依頼が多かった。それだけ、需要も多くなり世間一般にも普及し始めている証と言えるだろう。

友達がいない50代でも大丈夫!一人の時間を充実させる極意
ここまでは、50代からの友達作りに焦点をあててきたが、友達がいないままでも特に問題はない。
むしろ、一人が好きな人にとって中途半端な友達付き合いは、かえってストレスになってしまう。そのため、自分が本当に「好きなこと」を楽しめるかが重要だ。
最後に友達がいない50代が前向きになるために、一人の時間を充実させるための5つの方法を紹介する。
人生を振り返り「好きなこと」を明確にする
若い頃は「自分が本当に好きなことはなんだろう…」と迷うことがあった。しかし、50代は人生を振り返り、自分の得意だったことや興味があったことを考えてみれば「好きなこと」は見つけやすい。
たとえば、読書やゲーム、旅行や釣りなど一人時間を楽しめるものはいくらでもある。40代までは仕事やプライベートの忙しさに追われて、好きなことに時間を割けなかった人も、50代を機に自分だけの時間を楽しんでみてはどうだろう。
自分が楽しいと感じられる時間を増やしていくと、気持ちが前向きになり、生活に張りも出てくる。だからこそ、50代までの経験から「好きなこと」を明確にすることが、一人の時間を楽しむ一歩となるはずだ。
50代でも一人の時間を楽しめる場所を見つける
50代における一人時間を充実させるには、「好きなこと」を踏まえて、自分に合った居場所を持つことが大切だ。
一人時間を過ごすのに最適なカフェや図書館のほか、最近ではおひとりさま向けの飲食店や娯楽施設も増えている。
一人で行動することで「孤独で寂しい人」と周囲の目が気になることもあるかもしれない。しかし、友達がいない50代の多くは、本当は一人でいる時間が好きなことも自覚しているはず。余計なことは考えず、一人時間を楽しめば良い。
同世代と比較せず自分だけの価値観で暮らす
50代は仕事もプライベートも、自分の将来がほぼ確定する時期だ。それだけに人生の勝ち組やら負け組やら、同世代と比較して落ち込むことがあるかもしれない。
本当は悪い人生ではないはずなのに、地位や年収、結婚や子供の有無、そして友達まで周囲と比較して「俺は負け組なのか…」と思ってしまうこともある。
しかし、「好きなこと」を楽しめていれば、そんな周囲との比較はどうでも良いこと。友達がいない50代だからこそ、自分だけの自由な時間は多い。周囲と比較して落ち込む暇があるなら、自由な時間を思う存分楽しもう。
50代の人間関係は程良い距離感を意識する
一人が好きだからといって、完全に人間関係をなくすことはできない。50代は仕事や近所付き合いなど、友達とは異なる人間関係を維持する必要がある。
仕事や近所付き合いで深い人間関係を築くのはストレスの元にもなるため、程良い距離感を意識しなければいけない。
友達がいない50代の現実を不安に思い、新しい友達を作りたいと感じている場合も同じ。50代にもなれば、すでに相手の人間関係はおおよそ出来上がっている。下手な期待をするのは禁物だ。
だからこそ、50代からは無理に関係性を強化するのではなく、気軽に付き合える距離感を保った方が快適な日常を過ごせるだろう。
老後の不安を思いつくままノートに書き出す
友達がいない50代で私のように独身であればなおさら、老後の不安が大きくなるのは否めない。
「病気になったらどうしよう」「老後資金は足りるのか」など考え始めると、誰も頼れる人がいないことに不安で頭がいっぱいになることがある。
そんな不安で頭が埋め尽くされてしまったときは、老後の不安を思いつくままノートに書き出すと良い。ジャーナリング(書く瞑想)とも言われ、不安や悩みを文字に起こすだけで頭の中がすっきり整理できる。
そもそも老後の不安は、友達がいない50代だけが襲われるものではない。ノートに書き出した文字を見ると「不安に感じるほどでもない」「考えたところでしょうがない」など、気持ちが楽になるはずだ。
老後の不安解消だけでなく、「好きなこと」「やりたいこと」「得意なこと」など、50代になった今の気持ちを書き出していくと、新しい自分を発見できるかもしれない。
まとめ:友達がいない50代だからこそ自由な人生を楽しもう!
50代で友達がいない事実に不安になることは否めない。しかし、余計な人間関係に悩まされず、自由に好きなことを楽しめるのは、本当は喜んで良いことなのではないか。
特に一人の時間を好む人にとって、人間関係が多ければ多いほどストレスも多くなる。50代で友達がいないのは、そんなストレスを避けてきた結果だろう。
それでも、友達がいない50代の自分に不安を抱くのであれば、中高年世代でも新しい人間関係を築く手段はいくらでもある。自由な時間を活かして、仕事や趣味等を通じて新しい友達作りをするのも悪くない。
友達がいない50代のままでも、新しい友達作りを目指す50代でも、周囲の声に惑わされず、自分の気持ちに素直になれば、残りの人生を自由に楽しめるはずだ。