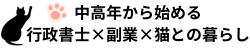行政書士の資格取得に挑戦しようと思ったものの、試験難易度の高さに「受かる気がしない…」と合格を諦めかけてる方も多いのではないでしょうか。
本記事を読んでいただいている方の中には、行政書士試験に挑戦して落ち続けている人や、過去問や模試の結果がボロボロで、2025年度の試験を受けるのは辞めようと思っている方もいるかもしれません。
行政書士試験の合格率は、わずか10%前後という難関の国家資格。特に40代・50代からの挑戦では、勉強時間の確保や記憶力の衰えなど、若い世代よりも合格のハードルは高くなります。
私は20年以上前に行政書士試験に合格しましたが、50歳を過ぎた今から資格挑戦するとしたら「受かる気がいない…」と分厚いテキストを見ただけで資格勉強を始める気すら起こらなかったかもしれません。
それは年齢だけの問題ではなく、今の行政書士試験は昔以上に合格が難しいと感じる理由があるからです。
本記事では、20年前と比較した行政書士試験に受かる気がしない理由とともに、今も昔も変わらない「合格できる人」と「合格できない人」の共通点をお伝えします。
中高年世代には無理ゲーとも思える行政書士合格のために、普遍的な「合格できる人」の勉強法もお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

2025年度の行政書士試験に受かる気がしない理由
行政書士試験に挑戦する多くの人が「本当に合格できるのか?」と不安になるのは、ごく自然なことです。
近年では、試験の難易度が上がったこともあり、合格するのは無理ゲーと感じる人も少なくないでしょう。
まずは、多くの受験者が共感できる行政書士試験に受かる気がしない理由について、私自身が体験した20年前の試験との比較も交えながら解説していきます。
試験科目の改正があった
2024年度より行政書士試験の試験科目の一部が下記の表のとおり改正されました。改正前の「行政書士の業務に関連する必要な一般知識等」の分野が改正後に「行政書士の業務に関し必要な基礎知識基礎知識」と変更され、下記のとおり実質的な試験科目は3つから4つへ増えています。
| 改正前「行政書士の業務に関連する一般知識等」 | 改正後「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」 |
|---|---|
| 政治・経済・社会 情報通信・個人情報保護 文章理解 | 一般知識(改正前の政治・経済・社会も含まれる) 行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法等) 情報通信・個人情報保護 文章理解 |
ただでさえ、試験対策がしにくい一般知識の試験科目が改正されたことにより、過去問などの参考材料も少なく、受験者の負担が大きくなるのは否めません。
私が受験した直後にも試験科目の改定があり、選択式に記述式が加わったことで試験の難化が叫ばれていました。
しかし、今回の改正では「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」など、行政書士開業後に役立つ科目に変更されているため、「ますます受かる気がしない…」とネガティブにならず、ポジティブな試験科目の改正があったと頭を切り替えるとよいかもしれません。
さらに試験範囲が広くなった
試験科目の改正の影響だけでなく、20年前でも「受かる気がしない」と感じた試験範囲がさらに広がって心が折れます。
市販の行政書士用テキストを手に取ると、その分厚さに圧倒される方も多いはず。20年前のテキストと比較すると、体感的にページ数は3割増の感覚です。
そのため、今の行政書士試験は勉強する時間に余裕がない限り、すべての試験科目を対策することは、困難な状況と言えるでしょう。
試験の難易度が上がっている
過去20年以上前に遡っても、行政書士試験の合格率は約10%前後を推移しており、大きな変化は見られません。
しかし、法科大学院生や予備校生の受験者数が増加したことなどの影響で、試験問題も難しくなり、合格基準の300満点中180点以上の得点を取ることは至難の業です。
実際、20年前とはいえ合格者の私が過去問や模試を受けても、太刀打ちができない問題も多く、今から勉強するのはキツイと感じます。
試験対策の情報量が多すぎる
ネットで行政書士に関する情報を検索するだけで、YoutubeやSNSのアルゴリズムに「行政書士試験に興味のある人」と認識され、次から次へと行政書士の関連動画やサイトが表示される時代です。
おすすめの教材や勉強法、本試験の予想問題など、目に触れた情報が気になって、勉強の時間が削られてしまうことがよくあります。
20年前は行政書士試験に関する情報は決して多くはなく、情報を集める苦労がありましたが、現在は試験対策に関する数ある情報源の取捨選択が合格の鍵になると言えるでしょう。
勉強時間の確保が難しい
40代や50代で会社でも責任のある立場になれば、日々の仕事に追われて資格勉強に取り組む時間がなく、「受かる気がしない…」と感じるのは無理もありません。
2年・3年とゆっくり時間をかけて合格を目指すほどの熱意も余裕もないため、行政書士に挑戦するのは難しいと判断する人も珍しくないでしょう。
ただし、今は昔よりも後述するネットを利用して効率的に行政書士試験の勉強ができる方法も増えているため、時間がないと挑戦を諦める前に効率的な勉強法を探すことにも目を向けてください。
20年前よりも行政書士合格のハードルは上がっていても、行政書士に挑戦する価値は十分にあります。ネット上の一部には「行政書士はやめとけ!」などネガティブな意見もありますが、そんな情報に振り回されるようであれば、受験を諦めた方がよいかもしれません。

今も昔も変わらない行政書士試験に「合格できる人」の共通点
どんなに行政書士試験を取り巻く環境が変わっても、今も昔も行政書士試験に合格できる人には共通点があります。
ここでは、参考にしたい行政書士試験に「合格できる人」の特徴に加えて、決して真似してはいけない「合格できない人」の特徴もご紹介していきます。
テキストや参考書を買い過ぎない
私は行政書士に合格するまでに2回受験をしていますが、不合格となった1回目の試験のときは、あれこれと目に付いたテキストや参考書を買い込み失敗した経験があります。
一般的に合格できる人はテキストや参考書を絞り込み、徹底的に使い込むことで内容を丸暗記するレベルになっています。
そのため、テキストや参考書は、自分が使いやすいと感じたものや長年売れ続けている信頼できるものから厳選し、1年間は浮気しないように取り組むことが重要です。
すべての科目で満点を目指さない
行政書士試験の絶対評価のため、全体の6割以上正解すれば合格できます。そのため、すべての科目で満点を目指す必要はありません。
合格できない人のよくあるパターンは、難しい科目に時間を取られ、どの科目も勉強が不十分となり、確実に点を取れる問題を間違って不合格となるケースです。
一方で合格できる人は、8割~9割正解すれば十分と判断して、得点しやすい科目に集中的に時間を割くため、ミスが少なく合格率も高いといえます。
過去問を繰り返し解く
昔からあらゆる試験対策の定番と言えるのが、過去問を繰り返し解くことです。私は合格者の中で、過去問に手を付けない人を見たことがありません。
5年分程度の過去問に取り組み、間違った箇所をテキストで振り返りながら知識を深めていくのは、限られた時間の中で効率的な勉強にもつながります。
法学初心者でなければ、過去問だけを繰り返し解いて行政書士に合格した人もいるほどで、試験対策の王道ともいえる勉強法を真似することは合格への近道と言えます。
スケジュール管理を徹底している
仕事やプライベートで忙しい中で、資格勉強のために安定的に時間を生み出すためには計画的なスケジュール管理が必須です。
ポイントは余裕を持ったスケジュールを組むことです。無理な学習計画を立てた結果、スケジュール通りに勉強が進まず、モチベーションが下がってしまうこともあります。
試験勉強に限らず、何事もできる人は結果を出すまでの期間を逆算してスケジュールを立てることが上手い人なのかもしれません。
最新の情報収集を怠らない
行政書士試験に関する最新情報の収集能力は、合格するための大きなアドバンテージとなります。
法改正や出題傾向の変化はもちろん、効率的な勉強法なども行政書士試験に合格するためには必要な情報です。
今はネットが普及したことにより、情報格差が広がっていることから、昔以上に情報収集の重要性は高まっています。
合格後の未来を描いている
行政書士試験に直接的な関係はないものの、しっかりと合格後の未来を描いて勉強をしている人は、合格へのモチベーションが違います。
「行政書士として独立開業したい」「法律関係の仕事に就きたい」などといった明確な目的意識があると、行政書士試験に受かる気がしないといったネガティブな発言もしなくなります。
一方で、なんとなく資格がほしい程度の人は、勉強も惰性になりがちで「合格は無理ゲー」と諦めてしまうことが少なくありません。
今の受験生が羨ましい!行政書士合格に導く勉強法
20年前の行政書士試験よりも合格難易度が高まっている一方で、「今の受験生が羨ましい!」と思えるほど、試験勉強がしやすい環境が整っています。
昔は高額な教材や通学講座を利用して学ぶことが主流でしたが、今ではネットから無料でも合格するための有益な情報が得られる時代です。
ここでは、今から行政書士試験に挑戦するなら、ぜひ試してみたいと感じた勉強法を紹介していきます。
ネットの無料コンテンツで学ぶ
行政書士試験の合格をサポートするYouTubeやブログなど、有益な無料コンテンツがネット上にあふれています。
条文や試験問題の解説動画など、テキストを読んだだけでは理解できなかった箇所を分かりやすく図解や具体例で説明してくれます。
受験者が苦手にする科目や問題は、需要も大きいことからコンテンツも多く、さまざまな角度からピンポイントで学べることも魅力です。
SNSで合格するための最新情報を得る
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSは、行政書士試験に役立つ最新情報をいち早く得ることができます。
行政書士の試験内容に関するものだけでなく、同じ受験仲間と交流しながら、勉強の進捗状況の発信をチェックすることもモチベーション維持につながります。
ただし、SNSは勉強時間を奪う諸刃の剣。時間を決めて活用ができないのであれば、SNSを見ないことも合格するために必要です。
生成AIを資格勉強の補助に使う
ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用すれば、条文の解釈を分かりやすく解説してもらったり、苦手分野の要点を整理してもらったりすることができます。
最近の生成AIは上手く言語化できないような質問にも、こちらの意図を汲み取って答えてくれるので、分からないことを放置せずその場で解決できるのも魅力です。
現時点で情報の正確性には注意が必要なものの、近い将来には、AIを上手く活用することが行政書士試験に合格するためには、必要不可欠な時代になるかもしれません。
オンラインで通信講座を受講する
通信講座は自分のスケジュールに合わせた柔軟な学習ができるため、特に忙しい社会人には利用価値があります。
通学の資格学校と遜色ない学習ができるのは、昔の教材だけが送られてくるような通信講座とは大きな違いと言えるでしょう。
人気の通信講座は、講義の繰り返し視聴や倍速再生で学習時間を短縮できるほか、オンラインでの質問などのサポート体制も充実しているため、行政書士合格への近道となります。
20年前にも行政書士の通信講座はありましたが、あまり魅力を感じる内容ではありませんでした。しかし、現在の通信講座は違います。ネットを利用した指導内容は通学課程と遜色なく、独学では学ぶことができない試験対策が行えます。
なお、今の通信講座のよさを知ったのは、行政書士開業に向けて実務講座を通信講座で受講したからです。通信講座や合格後の開業に興味のある方は、下記の記事もぜひご覧ください。

無理ゲーの行政書士試験を攻略!通信講座の7つの魅力
行政書士試験に「受かる気がしない」「もう無理かも…」と感じたときこそ、勉強法を見直すタイミングです。
特に独学に限界を感じたなら、通信講座の活用を検討してみてください。今の通信講座は講義を聞くだけではなく、スケジュール管理や質問サポート、仲間との交流など、多角的に学習を支えてくれます。
ここでは、行政書士試験の合格率を上げる通信講座の7つの魅力を解説していきます。
合格までのスケジュールが明確になる
行政書士試験に合格するには、一般的に1年以上の期間が求められるため、明確な学習のスケジュール設定が欠かせません。
通信講座では「いつまでに何をやるか」といった合格までのスケジュールが立てられていることが多く、自分で学習計画を立てるのが苦手な人でも安心です。
学習の進捗状況を把握できるスケジュール管理機能がある講座など、独自のスマホアプリを提供している通信講座もあるため、資料請求などでチェックしてみてください。
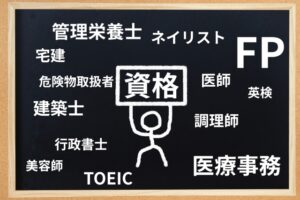
勉強を休むことができない強制力がある
行政書士の通信講座は、無料のYoutubeやブログのコンテンツとは異なり、数万円か数十万円の受講料が掛かるため、勉強に取り組む姿勢に強制力が働きます。
合格しなければ高い受講料が無駄になると思うと、独学では「今日は疲れたから勉強を休もう」なんて考えにはなりません。
通信講座を利用することで「勉強しなければいけない」と思う強制力によって自然と継続力が身に付くことは、効果を実感しやすい最大の魅力かもしません。
行政書士合格を目指す仲間を作れる
通信講座の中には、受講生同士がつながれるコミュニティ機能を提供している講座が多くあります。
孤独になりがちな行政書士の勉強も「同じ目標に向かって努力している仲間がいる」と思えることで、学習のモチベーションも高まります。
「テキストの○○ページまで進んだ!」「行政手続法の動画が分かりやすい!」など、同じ学習環境だからこそ共感しやすい点も見逃せません。
使用するテキストや参考書が絞れる
独学で勉強を始めると、書店の棚に並ぶ膨大なテキストや参考書の中から「どれを選べばいいのかわからない…」と迷うことは珍しくありません。
通信講座では、試験に必要な教材がセットで提供されるため、「このテキストに沿って勉強すれば大丈夫」という安心感があります。
テキストや参考書のほか、記述対策の問題集や法改正対応の別冊資料など、出題傾向を分析したオリジナル教材を使用していることもライバルと差が付くポイントです。
勉強で分からない点をすぐに確認できる
行政書士試験では、難解な判例の理解や記述式の正確な解答など、どうしても一人では解決できない疑問に直面することがあります。
通信講座のリアルタイムのオンライン授業や質問サポートなどで、プロの講師に直接疑問をぶつければ、的確な解答を得ることができます。
問題集の解答などに納得できず、モヤモヤした気分のまま勉強を続けることもなくなり、問題の理解が深まることは通信講座を利用する大きなメリットです。
試験対策の正確な情報を得られる
行政書士試験は法改正や試験傾向の変化が頻繁に起こるため、常に最新情報をキャッチして対策を講じることが重要です。
ネットでも情報収集はできますが、信憑性には疑問がある情報も少なくありません。間違った情報に振り回されるリスクもあります。
その点、行政書士の通信講座で提供される情報は信頼が置けます。通信講座の講師陣から試験の合格を左右するような有益な独自情報を聞ける機会もあるかもしれません。
行政書士試験の合格率が大幅に向上する
通信講座を受講する最大のメリットは、学習環境の整備によって行政書士合格の可能性が大幅に高まることです。
スケジュール管理、教材選定、疑問点の解消など、合格するために必要な要素を通信講座を受講することで解決することができます。
通信講座の中には、行政書士試験の平均的な合格率の3倍以上の実績を残しているコースもあり、本気で合格を目指す人にとって間違いのない勉強法と言えるでしょう。
【まとめ】行政書士試験に「受かる気がしない…」と感じたら勉強方法を変えてみよう!
年々難化している行政書士試験に合格するためには、効率的かつ戦略的な勉強が求められます。
「頑張っているのに成果が出ない」「模試の点数が伸びない」「もう無理かも…」と感じたときは、勉強法に問題があるかもしれません。
行政書士試験に「受かる気がしない…」と感じたときこそ、自分の勉強法を見直すチャンスです。
もし、独学を続けることに行き詰まりを感じているなら、行政書士の通信講座を受講することも検討してみましょう。