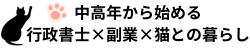行政書士開業について調べていると、よく「食べていけない」「仕事が見つからない」といった否定的な言葉を目にすることがあります。そんな言葉を真に受けて、開業に二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか?
私自身も50歳を目前に20年以上勤務した会社を辞めて行政書士開業を考えたときに思い浮かんだのは「安定している会社員と違って行政書士は生活していけるのか」という不安です。
しかし、開業準備を進めていく過程で、行政書士の仕事について深く調べているうちに、今では不安よりも楽しみの方が大きくなっています。
それは行政書士が食えないと言われる理由にも深くかかわる「資金」「実務」「集客」の3つの不安について、自分なりの対処法を見つけたからです。
これから行政書士開業を考えている方にの不安を少しでも解消できるように、前向きになれる情報をお伝えしますので、是非参考にご覧ください。
- 行政書士が食えないと言われる具体的な理由を知りたい人
- 行政書士開業前に感じる不安がどのようなものか知りたい人
- 実際に開業準備中に行っている不安の対処法を知りたい人
行政書士が食えないと言われる理由
「行政書士は食えない」という主張について、具体的な内容を解説します。
本当に行政書士は食えないのか?
以下はネットを中心に言われている主な行政書士が食えない理由になります。
1 平均年収が低く、廃業率が高い
➡仕事がなくて食べていけない……
2 法律系資格では難易度が低く、誰でも取れる資格
➡競合相手も多く勝ち残れない……
3 AIの進化により仕事が減っている
➡将来的に仕事が完全になくなってしまうのでは…
いずれも、もっともな理由ではありますが、行政書士が食えない根拠としては曖昧です。
1、2については、開業すれば行政書士に限らずリスクは高いもので、あくまで会社員と比較すれば安定していないということです。
平均年収や廃業率は明らかな統計データがあるわけではありません。競合相手が多いのも行政書士の資格取得という参入障壁がある時点で、一般的な起業よりも優位性があります。
そもそも、ラーメン屋(あくまで一例です)等の成功率と行政書士と比較すれば、「行政書士が食えない」というよりは、起業そのものが簡単ではないということです。
また3については、そもそも行政書士に限らず、早かれ遅かれほとんどの仕事はAIによって淘汰されてしまう時代が来ると言われています。
結局のところ行政書士が食えないのではなく、独立開業で成功するか否かは「人による」という結論になります。
下記の記事は、世間で言われてるより「行政書士はすごい」についての参考記事になります。
関連記事:行政書士合格はすごいのか?資格取得から20年目の真実

AIが進化しても行政書士業務はなくならない
とはいえ、もっとも気になるのは「行政書士の仕事がなくなるのでは?」と言われていること。いずれはすべての仕事がAIに淘汰されるといっても、行政書士の主要業務となる許認可関係の書類作成ソフトが販売される等、仕事内容からもいち早く影響を受けやすいとされているからです。
そこで、AIに行政書士の未来を考えてもらいました。質問内容は「行政書士の仕事はAIの進化によってなくなる?」というもの。以下は、ほぼ修正なしのAI(チャットGPT)による回答です。
行政書士の仕事は、AIが進化してもなくなることはないと考えられます。理由は以下の通りです。
chatGPTの回答より
- 行政書士の仕事には、法律や条例など複雑な規定が存在します。AIは学習に使用されるデータに偏りや不正確な情報が含まれる可能性があるため、人間がAIの結果を確認し修正する必要があります。
- 行政書士の仕事は、秘匿性があり個別具体的な情報を扱うことから適切に対応するために人間の判断が必要です。
- 行政書士の仕事には、適切に処理するためには官公庁とのやり取りが必要な場合があります。これらのやり取りには、人間同士のコミュニケーションが欠かせません。
どうでしょうか? ぐうの音もでない見事な回答といえるのではないでしょうか。
とはいえ、AIから将来の行政書士の仕事にお墨付きをもらっても、開業に対する不安が消える訳ではありません。そこで、次に私自身が現在感じている開業不安に対する具体的な内容についてお伝えします。
行政書士開業に対する3つの不安
私が脱サラをして行政書士開業を目指したときに感じた不安は、大きく分けて「資金」「実務」「集客」に関する3つ。行政書士開業時のよくある質問として見かけることも多い3つの不安について、具体的な内容を解説します。
資金の不安
資金に関する「よくある質問」として…
- 行政書士の開業資金は?
- 行政書士の毎月の運転資金の目安は?
- 行政書士の年収はどのくらい見込めるのか?
上記に関して書籍やネット等でいわれているそれぞれの目安となる回答は…
- 開業資金は、行政書士登録料や会費等で約30~100万(事務所賃貸料等により異なる)
- 運転資金は開業後に半年間無収入でも生活できる金額
- 年収は、行政書士全体の平均年収は約300万。初年度は収入0を覚悟するつもりで…
行政書士開業は一般的な起業と比べれば、開業資金や運転資金は少ないといわれます。それでも、開業後、仕事がなく収入を得られない状況が続けば、いつ資金が底をついてしまうか不安は尽きません。
実務の不安
実務に関する「よくある質問」として…
- 実務の知識・経験がまったくないけれど大丈夫か?
- 実務を相談できる士業の作り方は?
- 実務の学び方はどうするのか?
多くの行政書士の先生方は実務に関する質問の回答として、開業して経験を積むことが大事とよくいわれます。
しかし、実務知識がほぼ0の状態で開業することは勇気がいるものです。前述した資金の不安は、金さえ用意できれば解決する問題ですが、実務はそうはいきません。
まずは開業して経験を積むことが近道であることは理解できても、特に未経験・コネなしの人にとっては「そうは言っても、いきなりの開業は不安がある」というのが本音ではないでしょうか。
集客の不安
集客に関する「よくある質問」として…
- ホームページは必要なのか?
- コミュニケーション力がなくても大丈夫なのか?
- そもそもベストな集客方法は何か?
いまや弁護士でも、資格があるからといって集客できる時代ではないと言われます。ましてや、弁護士や税理士等と比較すれば、世間一般的には知名度が低い行政書士。お客さまをどのように集客するのか不安が大きくなるのは当然です。
行政書士開業を成功させるために、もっとも重要度・優先度が高く、力を入れなければいけないものが集客。いくら十分な資金力と実務能力があったとしても集客ができなければ意味がありません。
一方で集客が大事なことはわかっていても、資金や実務と比べると開業前の段階では実感しにくいのが集客不安。集客について考えることなく無暗に開業することは、行政書士開業を失敗する最大の要因になる可能性があります。
そもそもこんな不安だらけの行政書士開業を「なぜ50歳目前で20年以上勤務した会社を辞めてまで決断したのか?」については、下記の『40代・未経験・コネなし】脱サラして行政書士開業を決めた8つの理由』の記事で詳しくお伝えしています。良かったら参考にしてください。
関連記事:【40代・未経験・コネなし】脱サラして行政書士開業を決めた8つの理由

行政書士開業の不安対処法
ここからは私自身が実際に行っている「資金」「実務」「集客」に関する行政書士開業の不安対処法についてご紹介します。
資金に関する不安対処法
「資金」に関する不安対処法は以下の3つ
- 副業をする
- 融資を受ける
- 固定費を下げる
それぞれ具体的に説明します。
副業をする
行政書士の副業には以下の2つのパターンがあります。
会社員を続けながら、副業として行政書士をする
行政書士開業後に、副業としてアルバイト等をする
私自身は、前職が副業禁止であったこともあり、後者を選んでいます。しかし、もっとも安全で確実な開業方法を考えるのであれば、会社員を続けながら副業として行政書士でしょう。開業が上手くいかなかったとしても会社員としての収入があることは、これ以上ない安心感があります。
いずれにしても兼業となれば、行政書士業務に集中できないデメリットもありますが、資金繰りに悩みながら業務を行うことに比べれば問題は小さいはずです。
行政書士開業後に副業としてアルバイト等をすることに不安を感じる方は、以下の記事も参考にしてください。行政書士向けの副業を多数紹介しています。
関連記事:【中高年から始める副業】行政書士向け「攻めの副業」と「守りの副業」
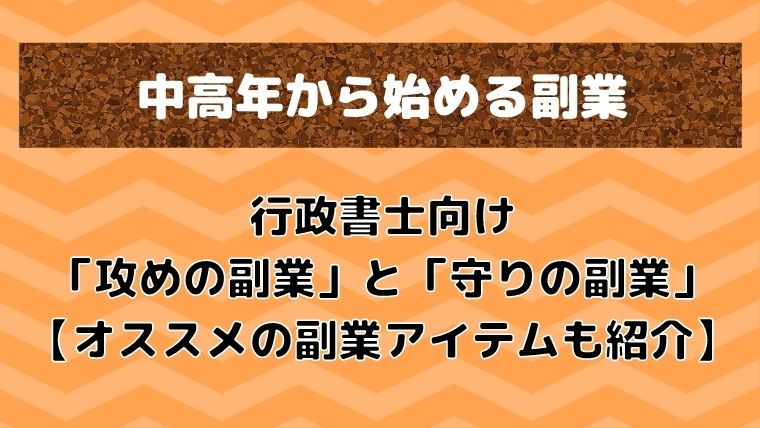
融資を受ける
融資と聞くと「開業前から借金をするのはちょっと…」と感じる方も多いかもしれません。しかし、融資を受けることには以下の2つの大きなメリットがあります。
- 金融機関との信用構築ができる
- 事業計画書の作成等、開業後の実務に活かせる
個人事業主となる行政書士は、開業時等に限らず金融機関の関係性が大事です。融資という形でも、期日を厳守した返済や、しっかりとした事業計画を示すことができれば金融機関からの信用は向上します。
なお、返済義務のない小規模事業者持続化補助金は、行政書士開業時に実務を学ぶ一環としても是非申請しておきたい制度です。
固定費を下げる
安定的に業務を行うためには、利益を増やすことも大事ですが、必要最低限に支出を押さえることはもっと大事。
一般的な家庭における収支と同様に、通常行政書士の固定費でもっとも大きな割合を示すのが事務所家賃。行政書士でいえば自宅開業をすることがもっとも有効な固定費を抑える手段となります。
自宅開業の「資金」に限定したメリットとして、家賃や光熱費等がかからないのはもちろん、必要に応じて一部を経費として計上できることも魅力です。
自宅開業の場合、自宅住所を公開される等のデメリットも考える必要はありますが「資金」に関することでいえば、そのメリットは計り知れません。
私自身も自宅開業の予定ですが、もし自宅開業ができなければ、そもそも行政書士開業の決断はしていなかったかもしれません。
実務に関する不安対処法
「実務」に関する不安対処法は以下の3つ
- 専門分野を決める
- 人脈を洗い出す
- 実務講座を利用する
それぞれ具体的に説明します。
専門分野を決める
行政書士の業務範囲が広いことから「覚えなければいけない実務が多過ぎる…」と不安になります。行政書士と名乗り仕事をする以上は、せめて行政書士の主要業務といわれている実務の基本くらいは押さえておきたいと思うからです。
しかし、現実的には、開業前で知識も経験もない段階では無理な話。どんなに優秀な人でも同じことです。とはいえ、何もできないのでは、さすがに不安。完全に専門分野とはいえないまでも、お客さまからの基本的な質問には対応できる程度の業務をつくることは大切です。
他の業務に関しては「専門外なのでお時間を少々ください」「他の先生をご紹介します」など、表向きでも行政書士業務の専門分野さえ決めておけば、お客さま対応も臨機応変にすることが可能になります。
関連記事:【開業準備】行政書士の専門業務を遺言書作成に決めた理由

人脈を洗い出す
行政書士の場合、行政書士事務所や他士業事務所で実務経験を積んで開業するケースは少なく、士業関係者の人脈を作ることが困難な現実があります。この背景を考えれば、開業前から士業の人脈をもっている人の方が珍しいでしょう。
私自身も士業関係のしっかりとした人脈はありません。しかし、これまでの人生を振り返ると、人脈といえなくもない存在に気付くことがあります。つまり、人脈を一から作るのではなく、これまでの人生経験から人脈を洗い出してみることで思わぬ関係性を見つけだすことができる場合があります。
私の場合の例をだすと…
- 父・母が亡くなったときに相続関係で業務依頼をした司法書士及び税理士
- 大学時代の友人が税理士事務所勤務
- 社員時代は官公庁からの受託業務がメインの仕事(公務員等の人脈)
①については継続案件があり、いまだに年賀状が届きます。②はそのまま。③は士業人脈とは異なりますが、実務の実態を知るには士業人脈よりも意味のある人脈になるかもしれません。
人脈というには遠いと言われるかもしれませんが、関係性が0の状態と比べれば、相手側も無下な対応はできないはずです。
もちろん、上記の人脈すらないと言われる方もいるかもしれません。しかし、友人・知人が士業に業務依頼したことがないか等、多少でも士業関係との繋がりがないか洗い出してみてはいかがでしょうか。40代以上の開業予定者なら尚更、過去の人脈を辿ることで意外な士業人脈がみつかるかもしれません。
関連記事:【開業準備】行政書士登録前からできる士業人脈の作り方5選
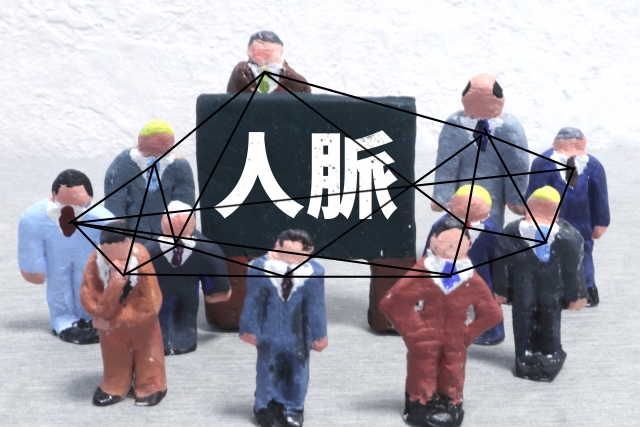
実務講座を利用する
行政書士の試験内容が実務にまったく直結しないため、実務のための学習法がわからずに不安になることがあります。しかし、ネットの普及とともに、行政書士の実務に関する情報も容易に見ることができる時代になりました。ネットだけでなく、行政書士の実務関連の書籍や講座も充実してきています。
一方で、情報の増加とともに、その情報を精査する必要性も高まっています。行政書士は、昔からヒヨコ狩りともいわれる新人行政書士に対する高額セミナーや商材販売等が蔓延っていた業界でもあります。より一層の注意をしなければなりません。そのなかで「確かな情報を得るためにはどうすればよいのか?」といえば、やはり実績のある実務講座で学ぶのが一番リスクは低いでしょう。
行政書士の実務講座を利用することで、実務の学びはもちろん、講師陣や生徒との人脈を作るきっかけにもなります。
関連記事:【開業準備】実務講座はコレ1択!伊藤塾「行政書士実務講座」を受講する9つのメリット

集客に関する不安対処法
「実務」に関する不安対処法は以下の3つ
- ブログを運営する
- SNSを利用する
- ホームページを作成する
それぞれ具体的に説明します。
ブログを運営する
一般的な会社員の場合、直接的に集客業務に携わることは決して多くはありません。そのため、集客方法についての知識がないことに不安を感じている人もいるのではないでしょうか。
集客について1から実践的に学びたいのであれば、ブログをするのがイチオシです。ブログのアクセス数を伸ばすためには、さまざまな集客・マーケティングの技術を必要とするためです。
「Googleサーチコンソール」や「Googleアナリティクス」等の無料の集客分析ツールを使用することにより、ブログのアクセス数やユーザー数はもちろん、性別、年齢、地域等、さまざまな情報を確認することができます。
また、どのようなキーワードで検索してブログを閲覧したのか等、ブログを多くの人に見てもらうために必要となる情報を収集できます。
これらの情報をもとにブログ運営をして、いかに集客を増やしていくのかは、後述するホームページ作成にもつながる実践的かつ有効な集客方法の勉強になります。
SNSを利用する
前述したブログ運営は、アクセスを集めるまでに最低でも半年以上の時間が必要と言われています。また、良質なコンテンツを作らなければ、1年経ってもGoogleの検索エンジンに評価されず、アクセスが殆どないこともあります。
その点、Twitter等をはじめとするSNS運用であれば、投稿内容次第でいきなりバズって、数多くの「いいね」を集めることも可能。ターゲット層を明確にして、投稿内容にも一貫性を持たせることで短期間にフォロワーを増やすことも決して難しいことではありません。
また、複数のアカウントを作ってABテストやPDCAを回すこと等の実験的な取り組みがしやすいことや、投稿に対する反応が早いため、結果がすぐにわかることも魅力です。
ホームページを作成する
行政書士開業後に集客のメインとなるものが事務所ホームページです。いまや多くの士業事務所がホームページを持っており、集客以前にホームぺージがなければ顧客からの信頼も得られない時代です。
「ホームページ作成なんて、簡単にできるものなのか?」と思われる方もいるかもしれませんが、前述したブログ運営とやり方は変わりません。ブログ運営で学んだ知識があれば、ホームページ作成自体は問題なくできるはずです。
ただし、ホームページもブログ同様にはアクセスを集めるのに時間がかかるため、なるべく開業前の早い段階で始めることが得策。ある程度アクセスが集まるホームページになっていれば行政書士の仕事依頼につながり、集客不安もだいぶ軽減されるはずです。
ホームページ作成のためには、サーバ契約やドメイン取得等の準備が必要になります。その手順は前述したブログ運営とまったく同じ。そのブログの世界で初心者の神とも言われるブロガーのヒトデさんの記事を読めば、簡単にブログもホームページも始めることができるはずです。
関連記事:ブログ初心者の神!ヒトデさんがすごい8つの理由【おすすめ記事と動画も紹介】

まとめ:【行政書士開業】食えないと言われる理由と不安対処法を体験談をもとに解説
行政書士開業をするにあたり、ネット上でよく見かける「行政書士は食えない」という話には、明確な根拠はありません。起業するのであれば会社員よりも安定性が低いのは当然で、むしろ資格取得という参入障壁のある行政書士の方が他の起業と比較すれば優位性が高いといえます。
とはいえ、開業時には主に「資金」「実務」「集客」の3つの不安を感じることがあります。しかし、私自身は以下の対処法を実施することで不安を軽減することができました。
「資金」に関する不安対処法
- 副業をする
- 融資を受ける
- 固定費を下げる
「実務」に関する不安対処法
- 専門分野を決める
- 人脈を洗い出す
- 実務講座を利用する
「集客」に関する不安対処法
- ブログを運営する
- SNSを利用する
- ホームページを作成する
私は現在、行政書士開業の準備をしている身です。そのため、開業後の現実はもっと厳しいのかもしれません。しかし、開業前の今だからこそ感じる思いや体験談が、少しでも同じく開業を目指している方の参考になれば幸いです